巻二十八第十五話には、海賊に襲われた僧が勇猛なことで有名な
伊佐の入道能観をとっさに名乗り、見事に海賊を追い返したという話がある。
頼れるものは自分自身の才覚だけであって、見破られて殺されるのも覚悟の上であれば、
嘘を突き通す度胸が本物であれば生き延びることもできる。
嘘をつくことが悪と言うよりも、一計を案じて相手を出し抜くことが美徳であって、
騙された人こそが悪だと、この話は語りかけてきている。
色仕掛けで医者を騙して患部を治療してもらい、治ったと同時に姿をくらました美女の話もまた
自分の器量一本で上手に生きてゆく人間を描いたものである。
色男の平中を焦らして恋煩いの末に殺してしまった女も、
機転があればこそ話の主人公となりえるものである。
貴族階級の日常が中心に描かれていた王朝文化では書き得なかった庶民の生活での知恵や、
個人の器量の大切さというものが今昔物語では明確に描かれている。
身分は低くとも、逞しく生きようとする生命力を捉えた話には
活き活きとした庶民の力を感じることができる。
これは現代でも共通することであって、一億総中流を目指せばよかった
バブルの時代が崩れ去った後の資本主義社会においては、
自分自身を売り込む能力がないと勝ち残ってゆくことができない。
今昔物語の生まれた平安時代末期のように、それまで隆盛していた貴族文化や
天皇支配という時代が衰退し、武士という新階級の台頭が
目前に迫ってきていた時だからこそ、新しいものが生まれる直前にあった。
我々の現代でも、経済優先・会社中心だった我武者羅な時代は崩れ、
環境保護や個人の時間を中心にして人々が暮らすように変化してきている今、
そこではやはり個人の能力が問われるのではないだろうか。
そうした場において、個人の力だけではなく神々の力を借りて
成功を収める場面があるのが今昔物語である。
伊香の郡司という話では、上司の国守から難題と引き換えに妻を要求された郡司が、
観音様の力を借りて難題を乗り切っている。
自分自身の力だけに限定せず他の力を借りようとも、
なんとか困難を乗り越えることは今昔物語での美徳である。
そこには仏教信仰の影響もある。
修行僧が性欲に負けて山奥で他人の妻を襲ったところを、
狩の最中に偶然通りかかった夫が獲物かと思って放った矢が、
修行僧に突き刺さる話には、個人の才覚というよりも
仏の力が難を逃してくれる、ということも描かれた。
巻二十七第三十六話では、墓場で鬼に襲われそうになった男が
どうせ死ぬのならば悪あがきしてみよう、と鬼に向かって太刀を振るった結果、
鬼だと思っていた大きな猪を倒して無事を得たという話がある。
流転する時代に巻き込まれ、死が身近だった時代に生きる人間たちは、
常に死を意識していたし、その死に抵抗しようと全力で運命に立ち向かっていった結果、
命を取り留めたという成功譚は今昔物語の代表的な美談だ。
古代の貴族社会から武士台頭の中世までには、
実に二世紀もの長い歳月をかけて緩やかに移行していった歴史がある。
藤原氏が摂政・関白を独占して政治の実権を握った時代から、
院政をひいた天皇が支配した時代、律令法による古代的な貴族・天皇支配の時代は長かったし、
その後の平清盛に始まる平氏の支配、源頼朝ら鎌倉武士が日本の政権を担う時代まで、
京都の貴族・皇族と地方の武士階級が支配を交代していった
長い時代の中から今昔物語は生まれている。
平家物語の盛者必衰の理を体現するかのように、繁栄しては衰退してゆく貴族たちに、
台頭してはまた別の武士に滅ぼされてゆく武士たち。
生も死も不確かな時代の中では、人々は王朝時代にあった優美なものよりも、
もっと身近でもっと人間臭いものを求めていったのではないか。
それが証拠に、今昔物語の本朝部に登場する主人公の多くは源氏物語のように
特権階級の人ではなく、一般庶民であるのだから。
貴族文化から生まれた王朝文学では、雅でないものには焦点を当たることは少なく、
美しいものが取り上げられている。そこに庶民の感情や生き様が入る余地はない。
今昔物語のような説話文学は王朝文学の対極に位置しており、
どんな低俗なものでも自分自身が直接目で見て確認しなくては引き下がれない、
という民衆の視点にまで下がってきている。
巻三十第一話で色男の平中が、どうしても自分のモノにできない美女に懸想をして、
恥ずかしがらせてやろうと便器を調べ、美女が仕掛けていた金の糞を見つけるのも、
幻想を幻想に終わらせるのではなく、
自分で最後まで解決しようした人間の行動が説話になったものだ。
王朝時代の人にもこうした行動があったのだろうが、それが文学に残るだろうか。
いや、風雅の世界に生きた人々がこうした話を文字に刻むことはなかっただろう。
グロテスクなシーンも今昔物語の世界では取り上げられている。
平貞盛は自分の悪性の瘡を治すためだけに胎児の生き肝を捜し、
息子の嫁の腹を裂けと言うし、実際に台所で働いている下女の腹を割いたりしている。
その上で、この治療法を教えてくれた医者を、己の出世と世間体のために殺して
口封じしようとするなど、あまりに惨い話までが生々しく語られているのも、今昔物語ならではだ。
この話だけが特殊だったのかもしれないが、少なくとも当時の人々の間では
こうした必死の生存競争が行われていたことを読み取ることができるし、
確かにその一部を今昔物語の話の中で垣間見ることができるのである。
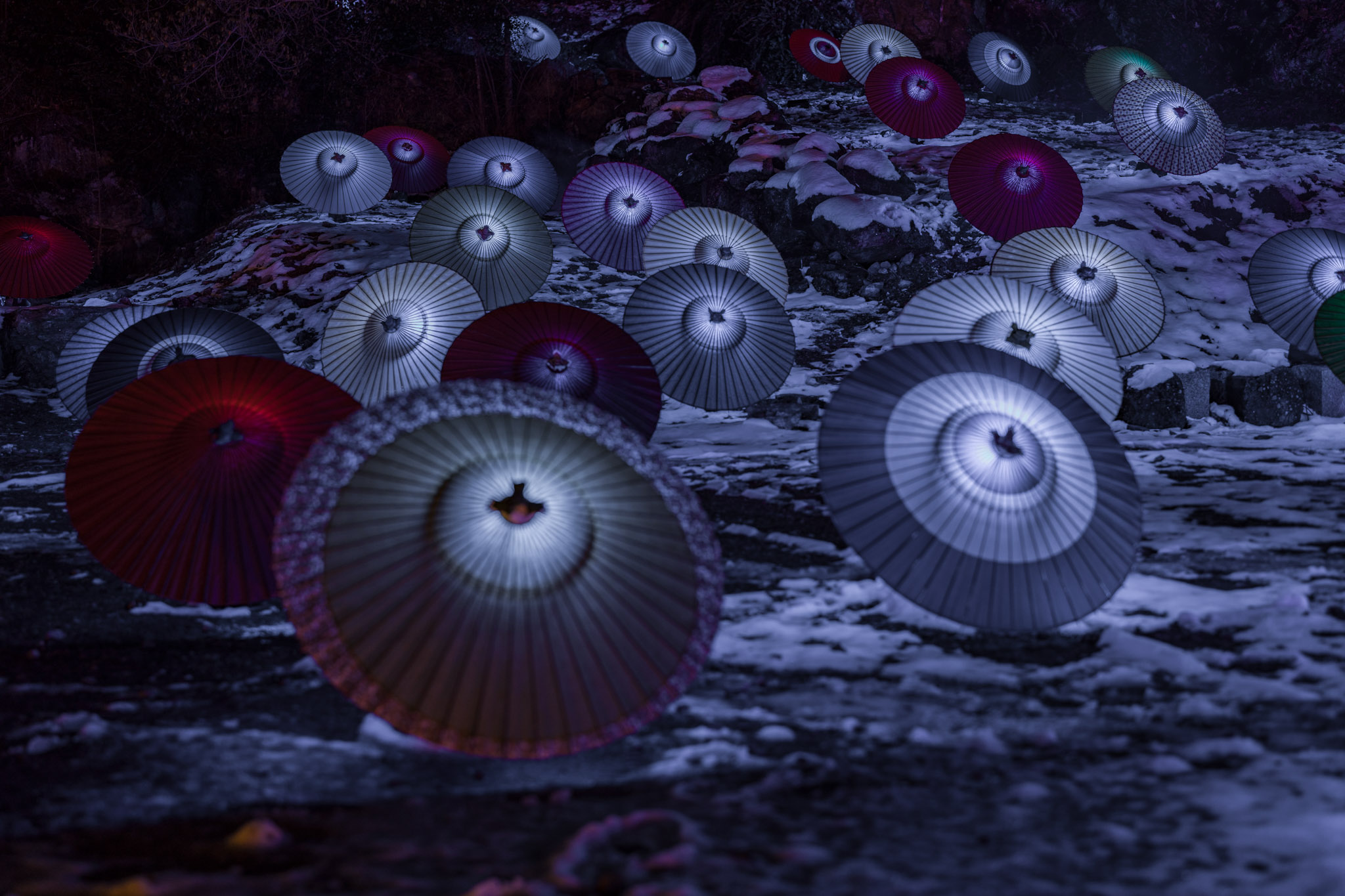
権力者の横暴もまたひどい。
中国の国王が百丈の卒塔婆を石工に造らせたが、
他国でも似たものが造られるのを阻止しようと、その石工を殺そうとした話には
権力者のエゴが隠しようがないぐらいに出ているし、その危機を石工夫婦が
機知で切り抜けた場面には庶民ロマンの軽快さがある。
古代では権力者からの強制を逃れる術を庶民は持たなかったが、
今昔物語が書かれた時代にはそれも個人の勇気と知力によって克ち得る可能性を秘めていた。
与えられた苦しみにも信仰心を持って耐え抜くことで救われるのは
受動的な仏教の救いの世界であるが、民衆は自分たちが能動的に行動することで
救いを獲得できるということを、身をもって知っていたのだ。
この人生の苦難の話と、美徳を美徳としてだけ書いた話を比べてみる。
物語の多様性を考えれば幸せと不幸の話が交互に散りばめられているのも
説話集には必要だとは思うが、どうしても美徳だけの話には奥行きが乏しく思えて仕方がない。
鬼や盗賊の姿を描く暗黒の物語に民衆の貧困を見ることができる。
無人の寺で賊から襲われた女性が、命こそ優先であるから諦めて犯される場面もある。
自分の子供を犠牲にして暴漢から貞操を守った別の女の話でも、
相手の男が乞食だったから子供の命と引き換えにしても
自分の身体を守ろうとしたと考えるならば、
身分階級こそがその女を突き動かしていたものと思うことができる。
今昔物語では話中に美人を登場させたいときに、風貌のどこが美しいかを描くことよりも、
生活様式の品位や全体の趣味で美人をイメージ付けたように、
やはり身分階級意識は当時の人々にとって強いものだったのだろう。
奪おうとした男も必死ならば、守ろうとした女も必死。
互いに必死を生きる中でも、当時なりの価値観によって人々は動かされていたのだ。
武士の力が眩しく描かれている。
巻二十三第十四話では、明尊僧正が三井寺へ往復する道中に
武人の平致経に警護を命じるが、出発姿では平致経と下人一人だけと
頼りない警護だったのだが、歩くごとに道脇から武士仲間たちが無言で共に加わってゆき、
終いには三十人もの黒装束の武士たちが警護していた。
目的を済ませて京都へ戻るにつれ、逆に仲間たちが無言で順に姿を消してゆき、
最後には平致経と下人一人だけとなった。
それらが無言のうちに行われたというところが、
武士たちらしい生死を賭けた訓練と以心伝心の賜物である。
まだ貴族支配の社会が残っている今昔物語の時代に、
刀の音を鳴らして歩いてくる武士の姿を取り上げたところに、
今昔物語の編者たちの先見の明を感じることができる。
古代では貴族たちには優雅こそが大事だという価値観があり、
今昔物語時代には何よりも命が大事だとする庶民的な価値観があり、
その先の中世では名を惜しめという武士たちの価値観がある。
その中でも一番強烈なものは、やはり何よりも命が大事だという
人間臭いらしい必死な動機ではないだろうか。
生き延びることへの執着心。悟りを開いて死に甘んじる仏教の姿ではなく、
貪欲に生きることこそが人間本来の美しさだと、今昔物語の編者たちは伝えたかったのだろうか。
それは世の仏教信仰とは相反する意識であるから、公にはできなかったものと推測できるのだが。
そもそも宗教には支配者層が権力を正当化するために便利なように作られてきた歴史がある。
中国の儒教は官僚支配構造のために生まれた歴史があるし、
ヒンズー教は階級社会を正当化するものだ。中世ヨーロッパの宗教改革は
上からの束縛から脱出するために民衆が巻き起こした運動である。
鎌倉仏教は国家からの自立と個人の救済を趣旨として生まれたものであり、
この今昔物語の貧民たちもまた、崇高な仏教ではなく
純粋に人間解放を求めていたと捉えるともできる。
しかしながら、人間解放へと向かおうとしても当時はまだ闇の時代であった。
古代権力支配の力が残る中で、先が見えない民衆らは
それでも自由への道へと向かおうとする意思を持ち、
「今は昔」の仮の物語を組み立てることで将来を模索し、解放への道筋をつけようとしたのではないか。
「今は昔」の言葉を額面どおり捉えれば過去のことを言っているように思われるが、
実際は過去にまぎれて自分の将来を仮定しようとしたのではないか。
千話に及ぶ膨大な説話集を一人の人間の人生で体験できるものではない。
人は自分が経験したものしか書くことができないのだから、
編者が呼び止めた人から珍しい諸国の話を聞いて書き留めたものに
手を加えて編纂したのが、この今昔物語なのであろう。
今昔物語には真面目な徳を描いた話もあるが、わたしにはどうも興が失われている気がする。
巻十六第二十話には、勇敢な夫が相手に騙されつつも、
妻の機転によって好機を得て相手を退治するという、
若い夫婦が協力して困難を脱してゆく美しい話がある。
強い夫とそれを支える妻という、日本の理想的な夫婦のあり方には違いないが、
他の話では生々しい人の欲望や生き様があり、言わば醜さと美しさが矛盾なく同居して、
それが不思議と輝いているのが今昔物語の魅力であろう。
美徳だけが強調されているところを見て、
今昔物語を知った気になるのは片手落ちと呼ぶべきものだ。
運命の非情さにも容赦がない。
貧しさゆえに別れた前の夫とは知らずに、また結ばれたことに気付いた女が、
わが身の不運を思って息途絶えてしまった話なども、容易に幸せな結末に結び付けず、
そこで死を迎えさせてしまったところに今昔物語の厳しさがある。
同じく貧しさゆえに別れた男女のうち、別の豊かな男にもらわれた女が、
農作業中の落ちぶれた元夫を偶然見つけてその貧乏に同情し、着物を与えた。
そしてそのまま東と西に生き別れる男女の、なんとも残酷の時の流れ。
希望を与えずそのまま冷たい運命に引き裂かれて話を終わらせるところに非情さを伺うことができる。
この説話集に所収された話の量は格別であり、それまで巷にあふれていた仏教説話を
ほぼ網羅しており、古代日本における仏教説話集の様相さえある。
それも主役は人間だけではなく、動物や信仰までもが主役になりえたということは、
世界は人間を中心としては回っているわけではなく、
神々や精霊など人間が制御できない何か大きな輪廻転生のようなものが支配していた、
いう考え方に違いない。
それまでの裕福層を中心とした物語とは変わって、一般庶民から僧侶、賊から武士、
貴族に天皇、菩薩から鬼や蛇など様々な立場に沿って書かれている。
そこには本当の意味での主役が存在しない。
王朝文学に本当に共感できたのは限られた裕福な貴族層だけであったのだろうが、
今昔物語では庶民を含む世間一般全体が読者になる可能性を秘めるようになっている。
全ての人が読んで、全ての人が登場人物になりえて、全ての人が笑われる立場になる。
今日笑っている自分が、一歩間違えば明日には
笑われている自分になるかもしれないという危うさは、明日死んでも不思議ではない、
と死をありふれたものとして受け止めていた当時の人々には身近なものだったのかもしれない。
混沌とする時代の中で、人々は現在や未来がどうなるか予想ができなかった。
今は昔、として昔を例にあげる方法が精一杯だったのだろう。
太平記や平家物語が今を生きる人間に焦点をあてて自分の身の回りの
人間像を描いたのとは違い、今昔物語では昔に生きた人間として話を組み立ててゆくなかで、
故人たちを非難してもしかたないことであるから、そういう人物が過去には存在したのだ、
という事実を描き、それは必然的にありとあらゆる人間像を
描き出す物語を完成させることにつながった。
古代から中世への変化を記録した物語。
王朝文学にはなかったもので、後の人間解放の中世文学を生み出す源が潜んでいて、
文学の時代と時代をつないでいるもの。
和漢混在の文体で書かれているところを見ると教育があった著者だったのだろう。
庶民の必死な生き様のようにグロテスクなものは貴族には書けないはずであるから、
当時の文化層である寺院の僧侶階級が書いたものだろうと想像がつく。
印度・中国の仏典までも引用しているのだから、仏教の僧が関係していた間違いないだろう。
源隆国の宇治大納言物語など、いくつもの書物が出典と考えられているが、
それにしても膨大な物語の数は尋常ではないし、
そもそも編纂された意図さえも不明なのが今昔物語だ。
内外の仏教説話がまとめられているところから推測すると、
仏教僧による修行目的の書だったのかもしれない。
別の観点で言えば、混乱の世の中を憂う一人の人間として、
その時代を生きた証拠を残そうとしてまとめた書物なのかもしれない。
仮に複数の僧が作ったものとすると、ある程度の仏教の知識を持つ知識人たち、
それも現在を疑問視する人々で、かつ未来を切り開こうとする意思があった人たちなのだろう。
彼らは過去と現在を書物に封印するために今昔物語を作ったのか?
いいや、連歌や歌合いのように美しい連想を楽しむ、
一種の知的娯楽のような感覚でなかったのか。
そこではアイディアが現実を飛び越えてゆく。
元となった話に沿っていても、イメージはそこに閉塞されたものではなく、
互いに思い切った面白さを競い合うように新しい物語を生んでいったに違いない。
現世を未来に残そうとする意識よりも、ただ目の前の世界を物語に
詰め込んだだけだったと考えて不自然はないと思う。
野生の美しさ、と評した芥川龍之介の指摘は最もだ。
王朝文学の優美さは地に足がついていないのでつまらなく、
台頭した市民層による中世の文学も豊か過ぎてつまらない。
台頭せず、時代に流され、貧しいままの市民層の視点で描かれた物語、
田舎である東人を馬鹿にしている都人の笑いが聞こえたと思ったら、
東国の兵馬どもが勇ましく駆けてくる馬の音が聞こえそうであるし、
荒削りのままで洗練されていない文体は今昔物語の魅力である。
所詮、王朝物語は限られた貴空間だけで行われていたものであって、世界が狭い。
それに引き換え今昔物語には当時の世界まるごと、庶民生活から宗教世界まで、
京都周辺を中心とはしているものの日本各地からアジアまで、
あらゆるものが詰め込まれたアートボックスなのである。
宗教が湿っぽく語られているかと思ったら、低俗な事柄が感情豊かに描かれていて、
全体的に陰気から笑いまで豊かに含んでいる。
地上の左右から高低まで、あらゆる人間の姿を地図に描こうとしたのが今昔物語ではないだろうか。
この説話集には人の醜さと貧しさが否定できず、そこに人の生命力の美しさというものまでが矛盾なく同居している。
この今昔物語の世界感の広さこそ、野生の美しさを感じさせてくれるものであるし、わたしがひきつけられた魅力的なものなのである。